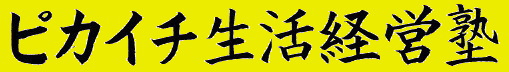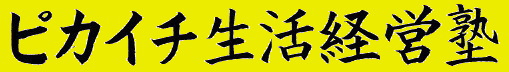|
実 験 室
ご 案 内
金銭教育
原発避難
家の除染
家の四季
複利計算

【企画・運営】
自立と創造のパートナー

ネクストライフ・
コンサルティング
|
|
安住財務相の「死んだ土地」発言が問題になり、ニュース番組は社会問題になる(テレビ局の意見)と伝えた。「死」という言葉がよろしくないようだ。
震災前まで、自分も「死=汚れたもの」という観念があった。理論で説明できない「死」が、理論主義の戦後教育では忌み嫌われ、よそ者扱いされてきた。「死」を排除することにより、「人間が考えた原理原則で社会を制御できる」と過信し続けてきた。
だが、今回の震災で「死」を五感で感じ、理論通りにならないい厳しい現実を知った。
息子(高3)の通う高校は、自衛隊の前線基地となり、体育館が犠牲者の安置所となった。現在、その体育館をそのまま利用している。
学校再開に向けて教職員と保護者で体育館を清掃したとき、校長先生が体育館の利用について説明した。
「自衛隊の皆さんが、」
「犠牲になられた方一人ひとりを、」
「学校のプールできれいな姿にして下さり、」
「ここ(体育館)にお連れした。」
「犠牲になられた仲間を、」
「ここから皆で送り出しました。」
「ここは皆さんの家の居間と同じです。」
「汚れてなんかいません。」
学校再開のニュース映像を見て、息子が語った言葉を思い出した。皆が満面の笑みを浮かべ、再会を喜んでいた。
「その気持ちわかるよ。オレ達も同じことをした。」
「『お前死んだかと思ったよ』が冗談にならない。」
「でも、他に言葉が見つからない。」
「だから、笑いながら言うしかない。」
被災者にとって、死んだ仲間も日常の一部である。生かされた仲間は、不連続な日常に向き合い、毎日が必死である。
|

塾 長
(ピカイチ先生) |
|
|