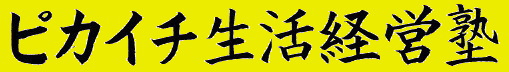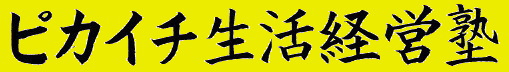|
実 験 室
ご 案 内
金銭教育
原発避難
家の除染
家の四季
複利計算

【企画・運営】
自立と創造のパートナー

ネクストライフ・
コンサルティング
|
|
小学校から帰宅するとすぐに、私は10円玉を一個握りしめて駄菓子屋へ向かった。遊び仲間と、[もんじゃ]を食べる約束をしていたからだ。
小学3年生のころ、母の内職の手伝いを始めた。一日10円のお小遣いでは足りないからだ。作業の[やりかた]を母から習う。内職の内容が変わる度に、新しい作業を習った。作業の説明が終わると、母は告げた。
「この作業の駄賃は、一個〇〇銭だよ」
「(だから)〇〇個で1円だ」
「作業全体で一個〇〇円だ」
「お前の作業は、全体の〇〇分の一なので、〇〇銭だ」
駄賃は、すべて歩合制だった。[どのくらいやるか][いつやるか]は、自分で考え自分で決めた。ある日、母が自分と違う[やりかた]で作業をしているのに気づく。早速、母に理由を尋ねた。
「どうして、違う[やりかた]をしているの?」
「この[やりかた]は危険だ(お前がやると怪我する)」
「(だから)お前は[真似]してはダメだ」
「この[やりかた]は難しい(お前には上手くできない)」
「(だから)お前は[真似]してはダメだ」
ダメと言われないときもある。そのときは、母の[やりかた]を[真似]するか否かは、自分で考え自分で決めた。家庭という[場]の中で、五感で体験しながら、私はお金との接し方を学んだ。包丁やマッチと同様に。
親になり、母の[金銭教育]を引き継いだ。お金との接し方は多様化したが、家庭教育の本質は変わらない。的(目的)は、[自分で考え自分で決める]人間に育てること。第1の矢(手段)は、試行錯誤する[場]を提供する。第2の矢は、真似する[型](親の背中)を提示する。第3の矢は、子の[親離れ]より先に、親が[子離れ]する。
わが家の[金銭教育]も終盤を迎えた。10年前、わが家の[金銭教育]の奮闘記を書き始めた。息子が小学5年生、娘が小学2年生のときである。
この度、わが家の[金銭教育]の奮闘記を、『家庭だからできた、わが家の金銭教育』として整理した。[自立]を目指す皆様にとって、「自分で考え行動する」のに役立てれば幸いである。
|

塾 長
(ピカイチ先生) |
|
|